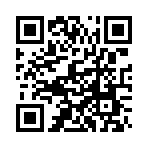2010年06月25日
県公文協
背中にのってる人は若干ちっちゃくなった感じがするものの、まだ身体を右に回すことができず。
午後、福岡県公立文化施設協議会の総会で講演。「文化施設と地域づくり」。出席者に館長クラスが多かったので、ちょっとひるみましたが、担当者を出す余裕がないところも多いのでしょうね。地域づくりのための人材養成も文化施設の重要な役割ですよ~と語りつつ、時間のかかる人材養成に取り組む余裕がないのが現場の実感だということもわかっているので、ジレンマを感じます。指定管理者制度導入以降、長期の構想を描けない館が増えたのではないでしょうか。本来は行政が公立文化施設の運営者にこうした事業に取り組むよう求めるべきだと思います。なのに。
先週末に市民ミュージカルの東京公演を成功させたサザンクス筑後の黒田館長も参加されていました。満席だったそうです。手ごたえをつかんだ満足そうなお顔でした。明日・あさっては筑後での凱旋公演。こちらも立ち見必至とか。チケットを早く買っておいてよかった。
午後、福岡県公立文化施設協議会の総会で講演。「文化施設と地域づくり」。出席者に館長クラスが多かったので、ちょっとひるみましたが、担当者を出す余裕がないところも多いのでしょうね。地域づくりのための人材養成も文化施設の重要な役割ですよ~と語りつつ、時間のかかる人材養成に取り組む余裕がないのが現場の実感だということもわかっているので、ジレンマを感じます。指定管理者制度導入以降、長期の構想を描けない館が増えたのではないでしょうか。本来は行政が公立文化施設の運営者にこうした事業に取り組むよう求めるべきだと思います。なのに。
先週末に市民ミュージカルの東京公演を成功させたサザンクス筑後の黒田館長も参加されていました。満席だったそうです。手ごたえをつかんだ満足そうなお顔でした。明日・あさっては筑後での凱旋公演。こちらも立ち見必至とか。チケットを早く買っておいてよかった。
2010年02月11日
春日市ふれあい文化センター嘱託職員募集
お知らせです。
福岡県春日市の文化ホール、春日市ふれあい文化センターでは、広報業務と事業の企画運営を担当する嘱託職員を募集しています。何を隠そう、私の後任です。私はNPOで業務委託を受けていましたが、後任の方は市の嘱託として雇用されることになります。
4月から大学教員の仕事が増えますので、春日市は卒業させていただくことになりました。引き継ぎ準備は万全です!
募集の詳細はこちら↓
http://www.fure-ai.or.jp/syokutaku.html
福岡県春日市の文化ホール、春日市ふれあい文化センターでは、広報業務と事業の企画運営を担当する嘱託職員を募集しています。何を隠そう、私の後任です。私はNPOで業務委託を受けていましたが、後任の方は市の嘱託として雇用されることになります。
4月から大学教員の仕事が増えますので、春日市は卒業させていただくことになりました。引き継ぎ準備は万全です!
募集の詳細はこちら↓
http://www.fure-ai.or.jp/syokutaku.html
2009年09月01日
リリックシアターから学ぶこと
ただいま帰りました。東京・あうるすぽっとで「学校と芸術をつなぐ実践ストラテジー」、新潟へまわって「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」へ。それぞれ簡単にご報告しますね。簡単に、と言いつつやっぱり長文になるでしょう。すみません。
まず「学校と・・・」
主催はNPO法人シアタープランニングネットワーク。英国・ロンドンの劇場、リリックシアター・ハマスミスが展開する青少年を対象とした活動やその背景にある劇場の戦略について担当者から直接話をうかがい、学校と芸術をつなぐコーディネーターの仕事に関わる考え方を学ぶ・・・ことが目的だったはずですが、講師が家庭の事情で直前に交代されたせいか、内容が募集時のアナウンスとはやや違うもので、リリックシアターの活動事例と戦略のお話がかなりを占めておりました。ただ、学べる点はいくつもありまして、私なりに留めておきたい点はこんな感じ。参加していない方にわかりやすいメモではありませんが、自分のための備忘録として書き残しておきます。
なお、下記にも出てきますが、リリックシアターは劇場としてのさまざまな活動を行うなかで、青少年のための、それも必ずしも演劇のプロを目指すわけではない子どもたちのために演劇を活用することに力を入れており、そこに他の劇場と異なる専門性を蓄積して社会的な認知を得ています。地域劇場のあり方のひとつの事例として大変興味深いです。
・子どもへの働きかけを行う活動の場面のうち、学校以外のカテゴリーのつくり方。リリックの場合、親子(「青少年」は14歳から18歳くらいを指すので、それよりも小さい子どもと親)、アーティストを目指す子とそれ以外の子が一緒に、アーティストの関与のもと行う活動(たぶん、内容もアーティスティック)、さまざまな事情があって劇場にアクセスできない子(社会的な課題がある子、虐待や犯罪を含む)、放課後のプロジェクト(子どもをストリートに野放しにしない)、仕事ベースの学習(ホールでの仕事につきたい子の就業経験)そして、それらをつなぐ活動、と設定している。
・アーティストが、対象である子どもに関する専門的な知識を有する必要はない。アーティストをソーシャルワーカーにする必要はないし、それでは劇場が劇場でなくなってしまう。ピアメンター(例えば、犯罪に手を染めてしまいそうな子にとって、同じ境遇から抜け出した少し年上のお兄さん)やプランをつくる専門スタッフが芸術以外の専門性を持ち、アーティストをそこにあてはめる。
・リリックでは、まず、子どもたちありき。集まった子の顔ぶれを見てふさわしいアーティストを決める。
・問題のある子にはピアメンターの存在は不可欠。ただし、すべてを劇場が抱え込むのでなく、他の専門家とのネットワークをきづいて、「ここから先は専門機関の仕事」と引き渡す。
・英国の手法はすべてポリシー、プリンシプル、そしてその運用法がきちんと文章化されている。このことがステークホルダーとの関係づくりにも生かされているように思える。
・英国のクリエイティビティ育成の考え方は、就労につなげるもの。だから、劇場の青少年向け活動でも、学校からはみ出してしまった子に資格認定を与えたり、上位の学校に行けるベースの学力認定が受けられるように考えられている。
・リリックは、社会に貢献する芸術に関わる活動をする、と方針を決めている。すべての劇場がその方向に行っているわけではなく独自の路線。このことがリリックの強みであり、ステークホルダーとの関係づくり、資金調達にもつながる。
まず「学校と・・・」
主催はNPO法人シアタープランニングネットワーク。英国・ロンドンの劇場、リリックシアター・ハマスミスが展開する青少年を対象とした活動やその背景にある劇場の戦略について担当者から直接話をうかがい、学校と芸術をつなぐコーディネーターの仕事に関わる考え方を学ぶ・・・ことが目的だったはずですが、講師が家庭の事情で直前に交代されたせいか、内容が募集時のアナウンスとはやや違うもので、リリックシアターの活動事例と戦略のお話がかなりを占めておりました。ただ、学べる点はいくつもありまして、私なりに留めておきたい点はこんな感じ。参加していない方にわかりやすいメモではありませんが、自分のための備忘録として書き残しておきます。
なお、下記にも出てきますが、リリックシアターは劇場としてのさまざまな活動を行うなかで、青少年のための、それも必ずしも演劇のプロを目指すわけではない子どもたちのために演劇を活用することに力を入れており、そこに他の劇場と異なる専門性を蓄積して社会的な認知を得ています。地域劇場のあり方のひとつの事例として大変興味深いです。
・子どもへの働きかけを行う活動の場面のうち、学校以外のカテゴリーのつくり方。リリックの場合、親子(「青少年」は14歳から18歳くらいを指すので、それよりも小さい子どもと親)、アーティストを目指す子とそれ以外の子が一緒に、アーティストの関与のもと行う活動(たぶん、内容もアーティスティック)、さまざまな事情があって劇場にアクセスできない子(社会的な課題がある子、虐待や犯罪を含む)、放課後のプロジェクト(子どもをストリートに野放しにしない)、仕事ベースの学習(ホールでの仕事につきたい子の就業経験)そして、それらをつなぐ活動、と設定している。
・アーティストが、対象である子どもに関する専門的な知識を有する必要はない。アーティストをソーシャルワーカーにする必要はないし、それでは劇場が劇場でなくなってしまう。ピアメンター(例えば、犯罪に手を染めてしまいそうな子にとって、同じ境遇から抜け出した少し年上のお兄さん)やプランをつくる専門スタッフが芸術以外の専門性を持ち、アーティストをそこにあてはめる。
・リリックでは、まず、子どもたちありき。集まった子の顔ぶれを見てふさわしいアーティストを決める。
・問題のある子にはピアメンターの存在は不可欠。ただし、すべてを劇場が抱え込むのでなく、他の専門家とのネットワークをきづいて、「ここから先は専門機関の仕事」と引き渡す。
・英国の手法はすべてポリシー、プリンシプル、そしてその運用法がきちんと文章化されている。このことがステークホルダーとの関係づくりにも生かされているように思える。
・英国のクリエイティビティ育成の考え方は、就労につなげるもの。だから、劇場の青少年向け活動でも、学校からはみ出してしまった子に資格認定を与えたり、上位の学校に行けるベースの学力認定が受けられるように考えられている。
・リリックは、社会に貢献する芸術に関わる活動をする、と方針を決めている。すべての劇場がその方向に行っているわけではなく独自の路線。このことがリリックの強みであり、ステークホルダーとの関係づくり、資金調達にもつながる。
2009年07月23日
東京公演
サザンクス筑後の久保田さん、山口さんとお会いしました。9~10月実施予定の事業や年間を通じた事業展開、友の会やボランティアのことなど、文化施設運営に関する幅広い内容でお話を伺いました。国民文化祭を契機に制作された市民ミュージカル「彼方へ 流れの彼方へ」、いよいよ来年6月、東京公演を行うことが決まったそうです。地方のホールが制作した市民参加型の作品が東京公演を行うというのは稀有な例ではないでしょうか。ぜひ成功させていただかねば。
2009年04月28日
世の人々の楽しみと幸福の為に
家族3人分のお弁当をつくっていて、6個入りミートボールを2袋、計12個温め、3つのお弁当箱に入れました。4つずつ。もうすぐ4月が終わります。1年の1/3が終わるんだ、と気づきました。ミートボールをあっためなくても気づきそうなもんですが。
久留米大の授業にお招きするゲストの方々と打ち合わせ。石橋美術館と石橋文化センターからおひとりずつ来ていただきます。いずれもブリジストンの石橋正二郎さんが地元・久留米の地につくられた文化施設。久留米大も、もともとは石橋氏が礎を築いた大学ですから、久留米大の学生はもっと美術館と文化センターに親しんでほしいです。それぞれの施設が久留米市においてどんな役割を果たしているのか、その経営はどのように成り立っているのか、市民のボランティアがどのように関わっているか、などをお話いただく予定です。お話くださるのはお2人ともはつらつとした女性。石橋美術館のGさんは昨年も講義においでいただき、学生の関心を掻き立ててくださいました。石橋文化センターのNさんは30数年にわたってセンターに勤務されていますが、今の文化センターが好き、とおっしゃいます。昔は遊園地のように遊びにくるところだった文化センターが、今は多くのボランティアに支えられ、たくさんの市民が憩う場所になっているから。入口に刻まれた石橋氏の言葉「世の人々の楽しみと幸福の為に」が本当の意味で実現しているように思うから。いいお仕事ですね。うらやましい。
久留米大の授業にお招きするゲストの方々と打ち合わせ。石橋美術館と石橋文化センターからおひとりずつ来ていただきます。いずれもブリジストンの石橋正二郎さんが地元・久留米の地につくられた文化施設。久留米大も、もともとは石橋氏が礎を築いた大学ですから、久留米大の学生はもっと美術館と文化センターに親しんでほしいです。それぞれの施設が久留米市においてどんな役割を果たしているのか、その経営はどのように成り立っているのか、市民のボランティアがどのように関わっているか、などをお話いただく予定です。お話くださるのはお2人ともはつらつとした女性。石橋美術館のGさんは昨年も講義においでいただき、学生の関心を掻き立ててくださいました。石橋文化センターのNさんは30数年にわたってセンターに勤務されていますが、今の文化センターが好き、とおっしゃいます。昔は遊園地のように遊びにくるところだった文化センターが、今は多くのボランティアに支えられ、たくさんの市民が憩う場所になっているから。入口に刻まれた石橋氏の言葉「世の人々の楽しみと幸福の為に」が本当の意味で実現しているように思うから。いいお仕事ですね。うらやましい。
2009年03月22日
吹奏楽クリニック
終日、春日。市民吹奏楽団が中学生の吹奏楽部員に技術指導をする「吹奏楽クリニック」のラストを飾る発表コンサート。写真撮影のためリハから見せてもらいましたが、指揮者の先生をはじめ、市民吹奏楽団のメンバーの方々が一生懸命に「伝えよう」とする姿に涙が出そうになりました。これだけの数の大人に、こんなにかまってもらえるこの子たちは幸せです。ほったらかしにされて荒んでしまう子もたくさんいる御時世なのに。たぶん、本人たちはちっとも気付いていないんでしょうけどね。
華やかさはないけれど、いい事業です。今年で3年目、かな? コンサートに来場されるお客様も増えました。アンケートによれば反応も上々。地域の公立文化施設、しかも教育委員会の直営館ならではの事業ですよ。
華やかさはないけれど、いい事業です。今年で3年目、かな? コンサートに来場されるお客様も増えました。アンケートによれば反応も上々。地域の公立文化施設、しかも教育委員会の直営館ならではの事業ですよ。
2009年02月02日
地域における劇場・ホールの使命と課題
午前。福岡アジア都市研究所で懇談。アジア太平洋都市サミット実施へ向けての企画段階とのことでヒアリングを受けました。こういう機関ともご一緒できるとおもしろいんですけど。
午後。九大HME(ホールマネジメントエンジニア)シンポジウム「地域における劇場・ホールの使命と課題」に出演。帝塚山大学の中川幾郎先生の基調講演のあと、アクロス福岡の小牧達彦さん、いわき芸術文化交流館の大石時雄さんとご一緒に短い講演とシンポジウム。県レベル、一般市レベルと規模の違うホールに関わる小牧さん、大石さんと、NPOの立場から話す私が異口同音に芸術文化を通じた地域振興の話をするという興味深い現象がおきました。3者の打ち合わせは全くしていないのですが。テーマが大きいのでいくつかの論点を提示するにとどまりましたが、HMEのプロジェクトは今年度始まったばかり。今後深めていくために論点の頭出しをする役目だったのだと思います。久しぶりにお会いした中川先生は以前よりも少し丸くなられ(?)ましたが、ホントのことをズバリおっしゃるところは相変わらず。お元気そうでなによりでした。
午後。九大HME(ホールマネジメントエンジニア)シンポジウム「地域における劇場・ホールの使命と課題」に出演。帝塚山大学の中川幾郎先生の基調講演のあと、アクロス福岡の小牧達彦さん、いわき芸術文化交流館の大石時雄さんとご一緒に短い講演とシンポジウム。県レベル、一般市レベルと規模の違うホールに関わる小牧さん、大石さんと、NPOの立場から話す私が異口同音に芸術文化を通じた地域振興の話をするという興味深い現象がおきました。3者の打ち合わせは全くしていないのですが。テーマが大きいのでいくつかの論点を提示するにとどまりましたが、HMEのプロジェクトは今年度始まったばかり。今後深めていくために論点の頭出しをする役目だったのだと思います。久しぶりにお会いした中川先生は以前よりも少し丸くなられ(?)ましたが、ホントのことをズバリおっしゃるところは相変わらず。お元気そうでなによりでした。
2009年01月18日
フルートコンサート
午前、春日で人形劇団クラルテによるワークショップ。24日(土)に「11ぴきのねこふくろのなか」の公演があるのにちなみ、人形劇の世界を知ってもらうための企画でもあります。物語の登場人物(?)であるネコやウヒアハになるべく紙で耳とかヒゲとかシッポをつくり、大きな新聞紙で作ったふくろのなかに入るシンプルな構成。単純に楽しい時間でした。
午後、宗像ユリックスへ。(財)地域創造の公共ホール音楽活性化支援事業で行われた「荒川洋フルートコンサート」を聞きに行きました。荒川さんとギターのマーチンさんとは、昨年、入間市での「おんかつ」でご一緒したし、宗像ユリックスは小野明子さん(Vn)片岡リサさん(筝)ペアで「おんかつ」を実施した際にアシスタントコーディネーターとしてご一緒したところ。荒川さんのフルート、マーチンさんのギターともに端正で清潔感あふれる演奏なので、ご一緒した入間市での数日間はとてもシアワセでした。今日のコンサートを聴きながら、やっぱりいいなぁと再確認。昨年、宗像で実施した「おんかつ」の担当者の方にお話を聞くと、ホールでのコンサートの前に地域で実施したミニコンサートのおかげでホールと地域のつながりが深まった様子。ものすごく手間のかかる事業なので、あとに残るものがないと大変すぎる気がしていたのですが、成果を感じ取っていただいているようなので、ホッとしました。今回も、地域でのミニコンサートを聴いてホールに足を運んだ方はかなり多かった様子。つれてきたお友だちに、荒川さんが宗像のために作曲した歌のことなどを一生懸命説明しているお客さまもいらっしゃいました。
終演後、荒川さん、マーチンさんにご挨拶して、用意してきた博多の棒ラーメンを手渡し。お2人とも「福岡に呼んでくださいよ」と言われていました。荒川さんはもつ鍋好きですしね。
午後、宗像ユリックスへ。(財)地域創造の公共ホール音楽活性化支援事業で行われた「荒川洋フルートコンサート」を聞きに行きました。荒川さんとギターのマーチンさんとは、昨年、入間市での「おんかつ」でご一緒したし、宗像ユリックスは小野明子さん(Vn)片岡リサさん(筝)ペアで「おんかつ」を実施した際にアシスタントコーディネーターとしてご一緒したところ。荒川さんのフルート、マーチンさんのギターともに端正で清潔感あふれる演奏なので、ご一緒した入間市での数日間はとてもシアワセでした。今日のコンサートを聴きながら、やっぱりいいなぁと再確認。昨年、宗像で実施した「おんかつ」の担当者の方にお話を聞くと、ホールでのコンサートの前に地域で実施したミニコンサートのおかげでホールと地域のつながりが深まった様子。ものすごく手間のかかる事業なので、あとに残るものがないと大変すぎる気がしていたのですが、成果を感じ取っていただいているようなので、ホッとしました。今回も、地域でのミニコンサートを聴いてホールに足を運んだ方はかなり多かった様子。つれてきたお友だちに、荒川さんが宗像のために作曲した歌のことなどを一生懸命説明しているお客さまもいらっしゃいました。
終演後、荒川さん、マーチンさんにご挨拶して、用意してきた博多の棒ラーメンを手渡し。お2人とも「福岡に呼んでくださいよ」と言われていました。荒川さんはもつ鍋好きですしね。
2008年10月27日
背中を押す何か
金沢21世紀美術館特任館長の蓑豊さんと、可児市文化創造センター館長の衛紀生さんの対談。のはずが、お2人それぞれのお仕事やその背景にある考え方を語っていただく時間が必要だったため、後半は会場との質疑に。質疑でもおもしろいやりとりがありましたから、参加者の満足度は高かったのでは? 参加者は約100名。主催者である福大商学部の学生さん以外にも多くの方が来てくださいました。そのなかで、特にこの分野の勉強をしているわけでもない普通の主婦の知人が、「とてもよくわかった。こういう創造的な考えで仕事をすること自体がアートですよね」と言ってくれました。彼女は何かやりたいことがあって、考えをまとめるためにいろんな刺激を受けたいと今日の催しに参加したのです。彼女の背中を押す「何か」があったお話、その企画に携ることができて満足。
福大商学部の田村先生、よく働く学生さんたち、お疲れ様でした。
金沢21世紀美術館 http://www.kanazawa21.jp/ja/index.html
可児市文化創造センター http://www.kpac.or.jp/ 「館長の部屋」をのぞいてください。
福大商学部の田村先生、よく働く学生さんたち、お疲れ様でした。
金沢21世紀美術館 http://www.kanazawa21.jp/ja/index.html
可児市文化創造センター http://www.kpac.or.jp/ 「館長の部屋」をのぞいてください。
2008年10月19日
バックステージツアー
終日春日。今日は「人財づくり講座」第2講。ふれあい文化センターの事業や施設のことを知っていただき、文化のまちづくりのために何ができそうか考えていただくネタ提供をしました。施設見学&バックステージツアーも組み込み、受講生の皆さんの予想以上のはしゃぎぶりにホクソ笑みましたよ。見学後は「思った以上にいい施設。でもそのことを市民はどれだけ知っているの? 知ってもらうためにナニができる?」という話題で盛り上がりました。センターの味方が増えた感じ。
2008年10月15日
表現する都市-美術館、劇場と都市との新しい関係
福岡大学商学部・田村馨教授のお手伝いで、下記のイベントの企画運営協力をさせていただいてます。
企画しといてナンですが、金沢21世紀美術館の蓑豊館長と可児市文化創造センターの衛紀生館長の対談で、スゴイと思うんですけど。平日昼間の開催ですが、みなさんふるってご参加ください。
*******************************
福岡大学商学部「表現する力をつけるプログラム」プレゼンツ
表現する都市-美術館、劇場と都市との新しい関係
ミュージアム、劇場は都市の集客力を支え担う施設の代表選手である。文化、アートに都市の魅力の源泉を求める創造都市論が90年代後半から注目を集め、ミュージアム、劇場の存在意義は高まりつつある。
半面、日本では、ミュージアム、劇場は「敷居が高い」か「特定の人のための」施設だとみなされる状況が、局所的には突破されつつも、大勢としては続いている。そのような状況が維持されているのは市民の意識の問題なのか、ミュージアム・劇場運営者のマネジメント・マーケティングの問題なのか、政府・地方政府の制度・人材の問題なのか。文化、アートに「都市の創客」を期待できる都市とそうでない都市があるとして、何が違うのか。その違いは埋められないものなのか。
本シンポジウムは、ミュージアム、劇場を巡る困難な状況を共有しつつ、そこから脱するために「各位がそれぞれの立場で踏み出すべき小さな一歩」を持ち帰ってもらうことを企図して開催します。
■プログラム
14時30分 主催者挨拶
14時35分~15時20分
講演「美術館が街を変える」
蓑 豊氏(金沢21世紀美術館特任館長)
15時20分~16時30分
対談「ミュージアム、劇場と都市の互恵関係を引き出す一歩を踏み出せ」
蓑 豊氏(金沢21世紀美術館特任館長)
衛紀生氏(可児市文化創造センター館長兼劇場総監督)
モデレーター:田村 馨
■日時:2008年10月27日(月)14時30分~16時30分(14時開場)
■場所:福岡アジア美術館あじびホール
(福岡市博多区下川端町3-1 博多リバレインセンタービル8F)
■定 員:120名
■参加費:無料
■申込方法:お名前とご所属(複数での申し込み可)を記して、メールまたはFAXで下記までお申し込みください。
○連絡先:E-mail timtamura@gmail.com FAX092-864-2938
福岡大学商学部 田村 馨 宛
■主 催:福岡大学商学部「表現する力をつけるプログラム」(代表 田村 馨〔福岡大学商学部教授〕)
■企画運営協力:アートサポートふくおか
企画しといてナンですが、金沢21世紀美術館の蓑豊館長と可児市文化創造センターの衛紀生館長の対談で、スゴイと思うんですけど。平日昼間の開催ですが、みなさんふるってご参加ください。
*******************************
福岡大学商学部「表現する力をつけるプログラム」プレゼンツ
表現する都市-美術館、劇場と都市との新しい関係
ミュージアム、劇場は都市の集客力を支え担う施設の代表選手である。文化、アートに都市の魅力の源泉を求める創造都市論が90年代後半から注目を集め、ミュージアム、劇場の存在意義は高まりつつある。
半面、日本では、ミュージアム、劇場は「敷居が高い」か「特定の人のための」施設だとみなされる状況が、局所的には突破されつつも、大勢としては続いている。そのような状況が維持されているのは市民の意識の問題なのか、ミュージアム・劇場運営者のマネジメント・マーケティングの問題なのか、政府・地方政府の制度・人材の問題なのか。文化、アートに「都市の創客」を期待できる都市とそうでない都市があるとして、何が違うのか。その違いは埋められないものなのか。
本シンポジウムは、ミュージアム、劇場を巡る困難な状況を共有しつつ、そこから脱するために「各位がそれぞれの立場で踏み出すべき小さな一歩」を持ち帰ってもらうことを企図して開催します。
■プログラム
14時30分 主催者挨拶
14時35分~15時20分
講演「美術館が街を変える」
蓑 豊氏(金沢21世紀美術館特任館長)
15時20分~16時30分
対談「ミュージアム、劇場と都市の互恵関係を引き出す一歩を踏み出せ」
蓑 豊氏(金沢21世紀美術館特任館長)
衛紀生氏(可児市文化創造センター館長兼劇場総監督)
モデレーター:田村 馨
■日時:2008年10月27日(月)14時30分~16時30分(14時開場)
■場所:福岡アジア美術館あじびホール
(福岡市博多区下川端町3-1 博多リバレインセンタービル8F)
■定 員:120名
■参加費:無料
■申込方法:お名前とご所属(複数での申し込み可)を記して、メールまたはFAXで下記までお申し込みください。
○連絡先:E-mail timtamura@gmail.com FAX092-864-2938
福岡大学商学部 田村 馨 宛
■主 催:福岡大学商学部「表現する力をつけるプログラム」(代表 田村 馨〔福岡大学商学部教授〕)
■企画運営協力:アートサポートふくおか
2008年08月16日
ピアノリレーマラソン
今日、明日と春日のイベント「ピアノリレーマラソン」。音響のいいホールでスタインウェイを市民の方に弾いていただくリレー形式の演奏会。2日とも約100組が演奏します。例によって午後は豪雨になりましたが、イベントに影響はなく、テレビ・新聞の取材も来てくれてまずます。明日17日(日)も11:00から17:00ごろまでやってます。無料です。11:30~12:00は別府アルゲリッチ音楽祭のプロデューサーとしても高名なピアニスト・伊藤京子氏のスペシャルトークと演奏があります。お得です。
イベント時は立ちっぱなしなので腰が痛い・・・
イベント時は立ちっぱなしなので腰が痛い・・・
2008年08月09日
大阪・金沢
7日8日と、受験生・長女のオープンキャンパスめぐりにつきあい、大阪・金沢へ。暑くてしんどいことです。合間を縫って両市のアートスポットもいくつか訪れました。應典院、精華小劇場、金沢21世紀美術館など。いずれもまちのド真ん中。生きているハコでした。
金沢21世紀美術館では、日比野克彦氏のアートプロジェクト「ホーム→アンド←アウェイ」方式 meets NODA【But-a-I】を見ました。NODAは野田秀樹氏のこと。ステージと客席が組まれていて、作品(ステージ上)を見てるお客さんを客席からほかのお客さんが見てる、という構造。よくわからずに入ったと思われる親子が数組。親御さんが「もうすぐ劇が始まるよ」と子どもを誘って入場したようですが、ステージ上では何も始まらず。しばらく客席に座っていましたが、「もう行こうか」とお父さんが立ち上がり、女の子が泣かんばかりに「げき見たかったぁー」と叫び続けるのがちょっぴりかわいそうでもあり、おかしくもあり。
金沢21世紀美術館では、日比野克彦氏のアートプロジェクト「ホーム→アンド←アウェイ」方式 meets NODA【But-a-I】を見ました。NODAは野田秀樹氏のこと。ステージと客席が組まれていて、作品(ステージ上)を見てるお客さんを客席からほかのお客さんが見てる、という構造。よくわからずに入ったと思われる親子が数組。親御さんが「もうすぐ劇が始まるよ」と子どもを誘って入場したようですが、ステージ上では何も始まらず。しばらく客席に座っていましたが、「もう行こうか」とお父さんが立ち上がり、女の子が泣かんばかりに「げき見たかったぁー」と叫び続けるのがちょっぴりかわいそうでもあり、おかしくもあり。
2008年04月27日
授業で石橋美術館見学
久留米大学の授業で石橋美術館見学を実施。日曜日ではありますが、最終講義の振り替えという形で行いました。美術の授業で絵を見に来たことはある、という学生もいましたが、今回は作品鑑賞が目的ではなく、「石橋美術館が久留米市で果たしている役割」を考えてもらうのが目的です。現在、石橋美術館では「もっと知る、美術」展を開催中。
http://www.ishibashi-museum.gr.jp/exhibitions/index.html
日本の近代絵画の流れを、作家の属していたグループなどの視点から構成して見せる展覧会。今日はボランティアさんによるギャラリートークで白馬会と二科会の紹介をしてもらいました。展覧会の見学のあとは普段入れないバックヤードに入れていただき、収蔵庫、書庫、機会室まで見せてもらいました。美術館といえば、展示されている作品を見るところ、というのがごく素朴な「美術館像」だと思うので、作品の収集・保存、調査・研究という機能もあることがくっきりと理解できる機会になりました。また、石橋文化センターの敷地内に移設されている坂本繁二郎アトリエの見学もさせていただきました。居心地のいいアトリエの中で、その修復費用捻出にまつわる努力についてお話をうかがい、経済学部の学生にも興味深い経験になったと思います。ご対応くださった石橋美術館の後藤課長さんには来月の授業にお招きし、さらに詳しいお話を伺う予定。やっぱり百聞は一見にしかず。行ってよかった現場体験でした。
http://www.ishibashi-museum.gr.jp/exhibitions/index.html
日本の近代絵画の流れを、作家の属していたグループなどの視点から構成して見せる展覧会。今日はボランティアさんによるギャラリートークで白馬会と二科会の紹介をしてもらいました。展覧会の見学のあとは普段入れないバックヤードに入れていただき、収蔵庫、書庫、機会室まで見せてもらいました。美術館といえば、展示されている作品を見るところ、というのがごく素朴な「美術館像」だと思うので、作品の収集・保存、調査・研究という機能もあることがくっきりと理解できる機会になりました。また、石橋文化センターの敷地内に移設されている坂本繁二郎アトリエの見学もさせていただきました。居心地のいいアトリエの中で、その修復費用捻出にまつわる努力についてお話をうかがい、経済学部の学生にも興味深い経験になったと思います。ご対応くださった石橋美術館の後藤課長さんには来月の授業にお招きし、さらに詳しいお話を伺う予定。やっぱり百聞は一見にしかず。行ってよかった現場体験でした。
2008年04月20日
市民参加型
午後。久留米市民会館の「音楽劇 久留米がすりのうた 井上伝物語」を見に行きました。春日の仕事で、この夏、ケンビの「アートにであう夏」展の関連イベントをアート・ボランティアさんと一緒に企画運営するので、その参考になるかと思って。それと、この事業が市民会館の指定管理者である業者さんの主催による市民参加型事業だったから。
会場は久留米がすりがいっぱい。スタッフや出演者はもちろん、お客さんも久留米がすりを着た方がたくさんいて、小さな子どものかすりワンピースも見かけました。あったかくていい感じ。ロビーに展示されていた機をマジマジと見ましたが、この作業はワタシには向かぬことを確認。あまりに細かく、オシリの痛い仕事だということがよく理解できましたから。
原作の「久留米がすりのうた」(岩崎京子著)を買いました。帰りの電車で半分読了。
会場は久留米がすりがいっぱい。スタッフや出演者はもちろん、お客さんも久留米がすりを着た方がたくさんいて、小さな子どものかすりワンピースも見かけました。あったかくていい感じ。ロビーに展示されていた機をマジマジと見ましたが、この作業はワタシには向かぬことを確認。あまりに細かく、オシリの痛い仕事だということがよく理解できましたから。
原作の「久留米がすりのうた」(岩崎京子著)を買いました。帰りの電車で半分読了。
2008年03月30日
しが文化サポーターズ会議
そして午後。「しが文化サポーターズ会議」へ。滋賀県内の美術館・博物館、公共ホールのボランティア、またはボランティアと協働している職員の方々が集まり、それぞれの取り組みの報告と交流を行う会議です。2月に実施された「気軽にどこでもアート交流事業」という、県内各地の文化施設が連携したイベントの振り返りをかねた催し。
「どこでもアート」は各文化施設が持っている体験型プログラムの見本市のような感じ。
詳しくはこちら↓
http://www.shiga-bunshin.or.jp/souzoukan/18_kigaruniart_top.html
サポーターズ会議は施設の種類や活動内容も多様で、大変刺激的。基調報告2人に実践事例の報告が14名とテンコモリの進行。私は勉強させてもらいに行ったのですが、報告者に回されてました。いや、いい機会をいただきました。ウチは文化ボランティアに関する活動をしているわけではありませんが、芸術家と学校・地域をつなぐコーディネーターの養成に取り組んでいることや、この取り組みから行政・公立文化施設のボランティア養成のお手伝いをする機会が増えていることなどを報告しました。ほかの皆さんの報告からボランティア同士のヨコのつながりが希薄だということ、ボランティアリーダー的な存在が育たないと企画立案から手がけるプロデューサー的な活動には展開しづらいことなどが見えてきました。風邪具合、ますます悪いのですが、行ってよかった滋賀県!
「どこでもアート」は各文化施設が持っている体験型プログラムの見本市のような感じ。
詳しくはこちら↓
http://www.shiga-bunshin.or.jp/souzoukan/18_kigaruniart_top.html
サポーターズ会議は施設の種類や活動内容も多様で、大変刺激的。基調報告2人に実践事例の報告が14名とテンコモリの進行。私は勉強させてもらいに行ったのですが、報告者に回されてました。いや、いい機会をいただきました。ウチは文化ボランティアに関する活動をしているわけではありませんが、芸術家と学校・地域をつなぐコーディネーターの養成に取り組んでいることや、この取り組みから行政・公立文化施設のボランティア養成のお手伝いをする機会が増えていることなどを報告しました。ほかの皆さんの報告からボランティア同士のヨコのつながりが希薄だということ、ボランティアリーダー的な存在が育たないと企画立案から手がけるプロデューサー的な活動には展開しづらいことなどが見えてきました。風邪具合、ますます悪いのですが、行ってよかった滋賀県!
2008年03月22日
サザンクス筑後「物づくり・街づくり・人づくり」
声の不調はしつこいセキへと進化。シンドイです。
午後、福岡市文化芸術振興財団の評議員の会議。理事会の前のワンクッション、という感じですが、もう少し活発な議論の場にしてもいいのでは?
夕方からサザンクス筑後。「物づくり・街づくり・人づくりシンポジウム」で、西鉄ホールの中村絵理子さんとご一緒にシンポジウム、というか、進行役のサザンクス筑後・久保田りきさんも交えて鼎談、かな? 演劇に取り組み始めた若い人たちが多い参加者に、演劇活動と地域がどうつながるのか、つなげるべきなのか、そのこととホールとの関係は? といった話をしたつもり。創り手の方、それも若い方に理解していただくには、舞台に立つ側だった自分の若い頃の体験談がいいかな、と思って、日ごろはあまり話さない個人的な経験もしゃべりました。中村さんや久保田さんが意外そうな目で私を見つめるヨコからの視線が痛かったなぁ。今日の集まりは、人数こそ多くはないものの、サザンクス筑後が時間をかけて取り組んできた人材養成事業の成果や可能性を感じることができました。
午後、福岡市文化芸術振興財団の評議員の会議。理事会の前のワンクッション、という感じですが、もう少し活発な議論の場にしてもいいのでは?
夕方からサザンクス筑後。「物づくり・街づくり・人づくりシンポジウム」で、西鉄ホールの中村絵理子さんとご一緒にシンポジウム、というか、進行役のサザンクス筑後・久保田りきさんも交えて鼎談、かな? 演劇に取り組み始めた若い人たちが多い参加者に、演劇活動と地域がどうつながるのか、つなげるべきなのか、そのこととホールとの関係は? といった話をしたつもり。創り手の方、それも若い方に理解していただくには、舞台に立つ側だった自分の若い頃の体験談がいいかな、と思って、日ごろはあまり話さない個人的な経験もしゃべりました。中村さんや久保田さんが意外そうな目で私を見つめるヨコからの視線が痛かったなぁ。今日の集まりは、人数こそ多くはないものの、サザンクス筑後が時間をかけて取り組んできた人材養成事業の成果や可能性を感じることができました。
2008年02月14日
直営館と「人」
全国公立文化施設アートマネジメント研修会/舞台芸術フェア・アートマネジメントセミナーに参加してきました。自腹で。13日からホントは明日15日までの日程ですが、スケジュールの都合で14日までの参加。4つのプログラムに参加しましたが、印象に残ったのは「自治体直営による地域文化施設の経営方法~直営館だからできる地域文化の振興とアーツの活性化を検証する~」のプログラム。パネリストが仙南芸術文化センター(えずこホール)の水戸雅彦さんと小出郷文化会館の桜井俊幸さん、コーディネーターが逗子文化プラザホールの間瀬勝一さん。いずれも直営館ですが、開館前から地域住民が文化施設のあり方について自ら研究するなどしており、行政にも文化振興の意義が浸透しているところ。しかもトップの彼らがリーダーシップを発揮して、一般に直営館(行政)のデメリットといわれる単年度会計や人事異動の問題をクリアしてしまっているという驚異的なところです。間瀬さんは、パネリスト2人のことを「デミリットをメリットに変える魔術師」と呼びましたが、まさにそのとおり。でも、その極意は「結局、人の問題」に落ち着いてしまうのは残念です。じゃあ、うちはムリじゃん、と思った参加者も多かったはず。なぜかの地には「人」がいて、わが方には「人」がいないのかを考えないといけません。私はえずこには行ったことがないのですが、小出郷はうかがいました。なぜ、「人」が生まれるのか。この地域は昔から「自分たちのことは自分たちで決める」風土があったそうです。人形劇フェスティバルで有名な長野県飯田市に行ったときも同じことを聴きました。飯田では、行政がいったんやめると宣言したフェスティバルを、市民が「自分たちでやる!」と宣言して継続させています。ここも、公民館が中心になって集落ごとの自治が浸透している土地柄だとのこと。長い長い年月をかけて出てきた「人」なのだろうな、と思います。私は文化施設の活動で「人」づくりに貢献することができる、と思うのですが、これもまた時間がかかることです。少なくとも何十年というスパンが必要で、3年や5年という指定管理者の指定期間では何も変わらないですよね。ああ、長い目で見ることができるのも「人」ですね。堂々巡りか。
2007年12月19日
おんかつ入間
昨日今日と埼玉県入間市に行ってました。(財)地域創造のおんかつ(公共ホール音楽活性化事業)の個別研修。本番(3月)を前に、アクティビティと呼ばれるアウトリーチ活動の会場下見やプログラム内容などを確認したり、アドバイスしたりするために伺うのですが、入間市の担当者の方はさばけるので、ご自分でどんどんできる感じ。アクティビティは小学校2校とシンプルだし、学校は音楽家の来訪を大歓迎ムードだし、いい感じでした。ホールが大きいので集客はがんばらないといけないかな。派遣される音楽家はフルートとギターのお2人です。
2007年12月07日
チラシ折込
原稿カキコの日々。夜はぽんプラザホール、「芝居屋コロシアム」に1月春日で行うワークショップ「バックステージ探検隊」のチラシ折込作業。チラシの数20枚ほど、1500組の折込にチラシと同じ数のヒトが来ているけど、これが遅々として進まない。チラシを読みながら回る折込作業って始めてでした。さすがに途中からスピードアップ、なぜか全部終わってないのに「終了」コールがかかって1時間半ほどで解散。あとはどうなるんでしょう?
「バックステージ探検隊」は、600席のホールのあんなとこやこんなとこを回ります。それだけじゃなくて、音響・照明・装置などの仕事を実際に体験しながら短い作品づくりまでやります。熊本の劇団きららさんにナビゲーターをお願いしているので、楽しいです。詳しくは春日市ふれあい文化センターのHPを見てね。小学4年生から高校生までが参加できます。定員30名の半分くらいがすでに埋まってます。春日市ふれあい文化センター http://www.fure-ai.or.jp
「バックステージ探検隊」は、600席のホールのあんなとこやこんなとこを回ります。それだけじゃなくて、音響・照明・装置などの仕事を実際に体験しながら短い作品づくりまでやります。熊本の劇団きららさんにナビゲーターをお願いしているので、楽しいです。詳しくは春日市ふれあい文化センターのHPを見てね。小学4年生から高校生までが参加できます。定員30名の半分くらいがすでに埋まってます。春日市ふれあい文化センター http://www.fure-ai.or.jp